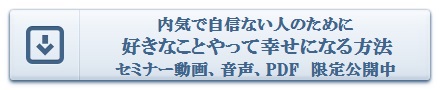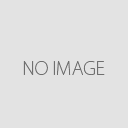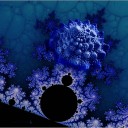未来型の生き方 ― 山籠り竹川の庵より

山に籠る意味と「未来型の生き方」とは
山に籠るということは、ただ人里を離れて静けさを楽しむことではない。
むしろ、日々のざわめきや世間の常識といった「音の洪水」から一歩身を引くことで、かえって心の奥深くに流れる微かな調べを聴き取るための営みである。
かつて鴨長明は『方丈記』の中で、こう書き残している。
> 「あだし野の露消ゆる時なく、鳥部山の煙立ちさらでのみ住み果つるならば、いかにもののあはれもなからまし。」
人の世に無常が絶えず訪れるからこそ、「もののあはれ」が生まれる。
露が消え、煙が立ち上る、その儚さを見つめるとき、人は逆に深い感受性に触れることになる。
山籠りとは、まさにこの「もののあはれ」に身を委ねる行為であり、未来型の生き方における第一歩でもある。
忙しさや効率を最優先にする現代では、あえて立ち止まることが「無駄」だと見なされがちだ。しかし、無駄に見える時間の中でこそ、人間の魂は澄み渡り、ほんとうにやりたいことの芽が顔を出す。
私自身、音楽の世界に身を投じ、都市の喧騒に押し流されそうになりながらも、山に籠ったことでようやく見えてきたものがあった。
それは「自分の声を取り戻すこと」である。
AIや機械が人間の代わりに多くを担っていく時代に、なお私たちが人間である理由はどこにあるのか。
答えは外の喧騒にはなく、山籠りの静けさの中、心の内に響く声にある。
そしてその声は、鴨長明が「露」と「煙」に見たように、移ろいやすく、儚く、しかしかけがえのないものである。
未来型の道を歩むとは、この儚い声を捕まえ、育み、現実に結びつけていくことなのだ。
仕事は我慢?「過去型の思い込み」を解く
「仕事は我慢するものだ」
「好きなことで飯は食えるわけがない」
多くの人が幼い頃に耳にしてきた言葉だろう。
これらは一見もっともらしく聞こえるが、実のところ未来型の生き方を阻む「過去型の呪縛」にほかならない。
心理学で言えば、これは **認知バイアス** のひとつだ。
親や社会から繰り返し刷り込まれた言葉は、脳の「網様体賦活系(RAS)」にフィルターを作り、可能性を見えなくさせる。
「できない」と思い込む心は、できる可能性を最初から排除してしまうのだ。
古事記の神話にたとえれば、それはまるで **天照大神が岩戸に隠れる**場面に似ている。
光を失った世界は闇に包まれ、人々は途方に暮れる。
しかし、神々の笑いや踊りが響いたとき、岩戸の奥に閉ざされていた光は再び姿を現した。
私たちの心も同じである。
「仕事は我慢」「夢は無駄」といった言葉に閉ざされると、心の光は岩戸の奥に隠れてしまう。
けれども、ほんの小さなきっかけ ― 誰かの笑顔や応援、あるいは自分自身の中に芽生えた「ほんとうはやりたい」という声 ― がその扉を揺るがし、再び光を呼び戻す。
私自身もその呪縛と向き合ってきた。
音楽で生きる道を選んだとき、父からは「音楽で飯が食えるか、馬鹿者」と叱責された。
しかし、たとえ反対されても心の奥底で確かに燃えているものを否定することはできなかった。
今振り返れば、その火こそが「未来型への入口」だったのだ。
哲学的に言えば、これは **「主体の回復」** である。
ハイデガーは人間の在り方を「ダス・マン(世人)」に流されることと、「本来的存在」に立ち返ることとに分けた。
過去型の言葉は私たちを「世人」としての在り方に縛りつける。
だが、未来型の生き方は「本来的な自分」へ立ち返る勇気から始まる。
過去型は「外からの声」に従う生き方。
未来型は「内なる声」に耳を澄ます生き方。
その差はわずかなようでいて、人生を根底から分ける分岐点となる。
やりたいことを封印しない ― 妄想・幻想が未来を生む
「そんなことできるわけがない」
「夢ばかり追っていないで、現実を見ろ」
誰しも一度は投げかけられた言葉かもしれない。
だが、真に未来を拓くものは、むしろ **妄想・幻想・空想** と呼ばれるものの中に潜んでいる。
ニュートンが万有引力を発見したのは、リンゴが落ちるという日常の出来事を幻想のように広げて考えたからだ。
コペルニクスが地動説を唱えたとき、人々は「そんなバカな」と嘲笑した。
だが「そんなバカな」が現実を塗り替えてきたのが人類の歴史である。
脳科学で言えば、この力は **デフォルト・モード・ネットワーク** のはたらきによって支えられている。
ぼんやりと夢想する時間に、脳は無意識のうちに情報を結びつけ、新しい発想を編み出している。
つまり「無駄」に見える想像こそが未来を形づくる土壌なのだ。
神話に重ねれば、それは **スサノオの荒ぶる力** に似ている。
暴風のように制御不能に思える力も、正しく生かせば新しい秩序を切り拓く。
やりたいことを押し殺すのではなく、時に荒々しい衝動のまま外に解き放つことが、未来型の芽を育む。
私自身、音楽の世界に身を置きながら借金を背負い、先が見えない時期があった。
それでも「やりたい」という声を封印せず、インターネットを通じて発信を続けた。
結果、山に籠りながらも遠くの人と繋がり、想いを分かち合い、道を開くことができた。
過去に封印した夢をもう一度掘り起こすことは、岩戸に閉ざされた光を呼び戻すようなものだ。
「本当はこうしたかった」という声を聞き取るとき、人は新たな勇気を得る。
そして、その声に従って一歩を踏み出せば、道は自然と拓けていく。
未来型の生き方とは、外から与えられた正解に従うことではない。
内に眠る「やりたい」という小さな灯火を消さずに育むこと。
それこそが、誰もが持っている最大の創造力である。
インターネットが広げるご縁と可能性
かつて人のご縁は、暮らす町や通りすがりの人との間に限られていた。
生まれ育った地域の枠を超えることは容易ではなく、夢を叶えたくても環境に左右されることが多かった。
だが、インターネットの出現はその常識を覆した。
一つの小さな投稿が、遠く離れた国の人の目に触れ、思いもよらぬ出会いをもたらす。
山に籠っていても、庵から発した言葉が海を越え、誰かの心を揺さぶることができるのだ。
実際に、過疎化した旅館が一人の外国人旅行者の偶然の訪問からよみがえったことがある。
その人はネットで見つけた風景に魅了され、滞在したのち、仲間や友人を呼び込み、やがては地域の文化を支える担い手となった。
また、途絶えかけた伝統芸能が、動画をきっかけに海外の弟子を得て、次世代へと引き継がれた事例もある。
こうした奇跡は偶然の産物ではない。
インターネットという「縁の器」に、私たち一人ひとりが自らの想いを注ぎ込んだからこそ生まれた必然である。
吉田兼好は『徒然草』でこう記した。
> 「心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。」
取りとめもなく心に浮かんだことを書き留めるだけでも、人の心を動かし、世に残ることがある。
兼好の時代には随筆がその役割を果たしたが、現代においてはインターネットがまさに「徒然草」の舞台となっているのだ。
私自身も、山に籠っていながら多くの人と繋がりを得た。
都市の喧騒を離れていても、心の声を発信することで共鳴が返ってくる。
そしてその共鳴が、さらに新しい縁を呼び込み、道をひらいていく。
未来型の縁とは、血縁や地縁に限られたものではない。
「想いを発信すること」で紡がれる共鳴の縁である。
そこには、距離も国境も存在しない。
魂の声が響き合うところに、真の繋がりが生まれる。
第五章 一発逆転より「磨き続ける道」を歩む
人は誰しも「楽して変わりたい」という誘惑に心を揺さぶられる。
「一発逆転の裏技がある」
「大富豪しか知らない秘密」
こうした言葉に引き寄せられては失敗し、また別の「近道」を探す。
私自身も、その罠に幾度も足を取られてきた。
けれども真実は、逆である。
「一発逆転」を狙うほど、人は逆に翻弄され、元の地点に押し戻されてしまう。
本当に人生を変えるのは、華やかな裏技ではなく、日々の地味で小さな積み重ねにほかならない。
寓話「ウサギとカメ」が語るのも、そのことだ。
一瞬の速さに酔いしれるウサギよりも、愚直に歩み続けるカメが最後には勝利を収める。
この物語は単なる子ども向けの教訓ではなく、未来型の生き方に通じる深い智慧である。
心理学でいえば、これは **習慣化の力** だ。
脳は繰り返される行動を「報酬回路」と結びつけ、やがて自然に続けられるようになる。
一夜で変わることはないが、日々の反復は確実に未来をつくる。
哲学的に表すなら、ニーチェが語った **「大地に根ざして生きよ」** の精神に近い。
宙に浮いた幻想にすがるのではなく、泥に足を取られながらも大地に根を張ること。
その逞しい姿勢こそが、魂を鍛え、未来型の道を切り拓く。
私も山に籠り、日々の暮らしの中で学んだ。
火を起こし、水を汲み、文章を書き続ける。
外から見ればささやかな営みかもしれない。
しかし、その繰り返しの中にこそ、心のリズムが宿り、やがて大きな実りとなって表れる。
未来型の道とは、「一発逆転」ではなく「磨き続ける道」である。
石を磨けば勾玉になるように、日々の鍛錬と歩みが魂を輝かせる。
そしてその輝きは、自分自身を照らすだけでなく、他者の心をも導く光となる。
未来型を歩んだ人の変化の物語
未来型の道を歩むとき、変わるのは環境や収入だけではない。
もっと深いところ――人そのものが変わっていく。
たとえば、ある人は「小説を書きたい」と願い、幾度となく賞に応募した。
しかし結果は落選が続き、やがて「自分には無理だ」と感じ、生きながら心が少しずつ萎えていくような時期もあった。
それでも学びと実践を積み重ねる中で、「小説とは異なると思っていた経験や学びも、実はすべて物語につながる」と信じられるようになった。
その歩みの中から、自分らしいスタイルの小説を見いだし、ついに一冊の本を出版するに至った。
また別の人は、仲間と共に学ぶ場で「自分のイラストは下手だ」と思い込み、他者と比べては自信をなくしていた。
ところが、その「拙さ」こそが自分らしさだと気づいたとき、絵を描くことがやりたいこととして立ち上がった。
やがてそのイラストは、一冊の本の表紙を飾ることとなり、想いを届ける象徴となった。
最初は「できるはずがない」と思い込んでいた人たちも、やりたいことに向かって歩み始めると、驚くほどの変化を遂げる。
これは単なる成功談ではない。
心理学的に言えば、**自己効力感**(自分にはできるという感覚)が高まることによって、行動が変わり、さらに成果を呼び込む。
その循環が、本人だけでなく周囲の人間関係までも変えていくのだ。
神話で言えば、それは **タケミカヅチの剣** に似ている。
国譲りの際、彼の剣はただの武器ではなく「国をひらく意志の象徴」であった。
同じように、自分の中に眠る「やりたい」という意志を抜き放つとき、人は自らの人生を切り拓き、周囲にも新しい秩序をもたらす。
私自身、数多くの人が変化していく姿を見てきた。
「無理だ」と思い込んでいた扉を開けると、その先には想像もしなかった景色が広がっていた。
そして、その景色を一緒に歩む仲間が現れる。
未来型の生き方は孤独な道ではない。
自分の魂の声に従う人同士が自然に共鳴し合い、互いを照らし合う。
だからこそ、一人の変化は波紋のように広がり、やがて社会をも変えていくのだ。
結び ― 未来型の文化を共に創る
AIが加速度的に進化し、私たちの生活の多くを担う時代になった。
単純作業や効率を追うことは機械に任せられるようになるだろう。
だからこそ、いま問われているのは「人間にしかできないこと」だ。
それは、魂の声に耳を澄まし、やりたいことを育み、誰かに伝えること。
一見無駄に見える想像、挫折や試行錯誤の繰り返し、心の奥に沈んだ小さな願い。
そうしたものを大切にし、形にしていくことが、人間ならではの営みである。
やりたいことを我慢して続けるのではなく、心から夢中になれることに取り組むとき、その姿は必ず誰かの心を動かす。
一人の変化が波紋のように広がり、社会に新しい風を吹き込む。
やがてそれは文化となり、未来をつくっていく。
未来型の生き方は、決して孤独な道ではない。
同じように魂の声を信じて歩む者たちが必ずどこかで共鳴し、出会い、支え合う。
山籠りの庵からでも、インターネットを通じてでも、その縁はつながっていく。
だからこそ、もしいま迷っている人がいたら、もう一度心の奥に問うてほしい。
「本当は、何をやりたかったのか」と。
その声は小さくとも、真実である。
一歩でも二歩でも、その方向に歩みを進めるとき、未来は必ず応える。
山に籠りながら、私が見つめてきたのはこの確信である。
未来型とは、特別な誰かのものではない。
すべての人の心に宿る声を育て、共に文化を紡いでいく生き方なのだ。
今日もここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。
また庵の風に乗せて、次の言葉を届けたいと思います。
内気で自信なく不安なあなたへ